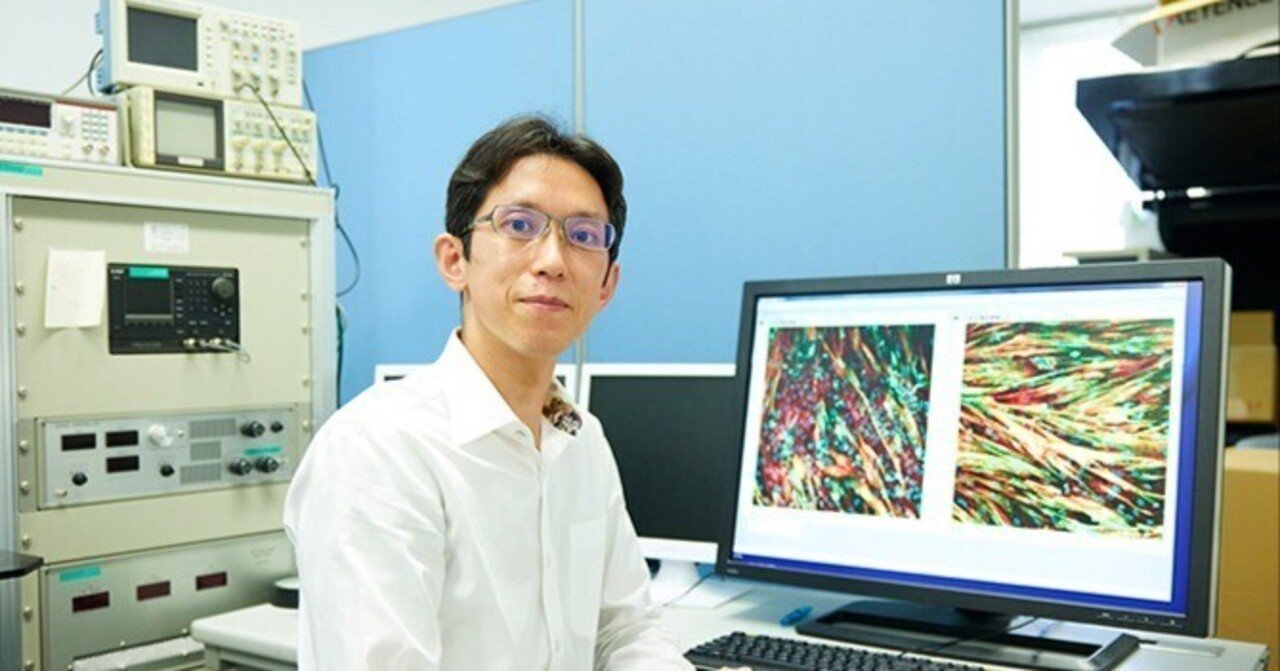ミクロからマクロまで、「音と身体」の関係に注目した記事
瀬良 万葉/合同会社展葉社 代表・演奏家
好きな音楽を聴くと、心が躍る。不快な騒音には、思わず耳を塞いでしまう。私たちは毎日、さまざまな「音」に囲まれながら暮らし、その影響を無意識のうちに受けています。
でも、「音と身体」の関係は、私たちが普段感じているよりも、もっと深く、もっと多層的なものかもしれません。音という「物理的な振動」は、私たちの身体の、一体どこまで届いているのでしょうか。
今回は4つの記事を道しるべに、生命の最小単位である「細胞」の世界から、音を使った身体表現の究極ともいえる「ダンス」の世界まで、「音と身体」をめぐる壮大な冒険に出かけてみたいと思います。
記事をおすすめした人

瀬良 万葉
1990年、兵庫県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了(音楽学)。2022年に合同会社展葉社を立ち上げ、文化芸術分野のイベント企画や広報支援などに携わる傍ら、ライフワークとしてオーケストラや室内楽での演奏活動も行っている。
私たちは、細胞で音を聴いているのかもしれない
私たちは、身体のどこで「音」を感じ取っているのでしょうか。多くの人は、耳の中にある鼓膜で振動を受け取り、それが脳に伝わって……というイメージを持っているかもしれません。
しかし、京都大学の粂田昌宏先生の研究によって、私たちの「細胞」一つひとつが直接「音」を感知し、応答している可能性が浮かび上がってきました。「非物質」としての音が、生命科学の発展の鍵を握っている可能性があるのです。
研究が進めば、生命にとっての音の本質的な意味が解明されるかもしれません。また、音は「身体の深部に安全に届くツール」として、医療に革命を起こす可能性も秘めています。
私たちが「聴く」という言葉で考える範囲を遥かに超え、生命の基本単位である細胞レベルで音との対話をめざす。そんな壮大な研究が、今まさに行われています。
ストレス社会への処方箋、音楽という名の良薬
細胞が音に応答するのなら、もっと複雑な音の集合体である「音楽」は、私たち自身にどう働きかけるのでしょう。大阪樟蔭女子大学で行われたシンポジウムのレポート記事は、この問いに「ストレス緩和」という切り口から答えてくれます。
記事によれば、好きな音楽を聴くと、私たちの脳内、特に生命の維持や本能、情動を司る「大脳辺縁系」が活性化するのだそうです。これにより、ストレスホルモンと呼ばれる「コルチゾル」の分泌が抑制されることが科学的に示されています 。
さらに興味深いのは、音楽がホルモンバランスを調整し、傷ついた神経細胞を修復してくれる可能性まであるということです。まるで、音楽が心身を最適な状態へとチューニングしてくれるかのようです。
ストレスの多い現代社会。日々の暮らしに、処方箋のいらない「良薬」として、音楽を取り入れてみたくなりますね。
私たちの身体は、世界に一つだけの楽器
ここまで、私たちの身体が音を「受け取る」側面を探ってきました。しかし、身体と音の関係は一方通行ではありません。私たちの身体は、音を「生み出す」こともできます。
その最も身近で奥深い例が「声」です。慶應義塾大学の記事「声のちから」では、合唱・オペラ指揮者、音声研究者、元アナウンサーという声のプロフェッショナルたちが、その魅力と秘密を語り合います。
記事によると、「いい声」に単一の定義はなく、物差しはさまざま。その人のキャラクターや人間性とも深く関わっています。そして、人生で刻んできた喉の皺一本一本が、その人だけの声色を作り出す。一人ひとりの声には、その人の生き方が現れているといえそうです。
私たちの身体は、単に音を発する「装置」ではなく、その人自身を映し出す唯一無二の「楽器」。この記事を読むと、普段何気なく発している自分の声に、もっと耳を澄ませてみたくなります。
世界と交信するメディアとしての身体
音と身体の関係性を、芸術の域にまで昇華させたのが「ダンス」です。筑波大学のコンテンポラリーダンサー・振付家である平山素子先生は、どの時代、国、民族にも歌やダンスの文化があると語ります。
平山先生にとって、ダンスは「原始的かつ効果的な意思の伝達方法」であり、「自分の中に潜んでいた感覚や感情が引き出されたり、そこから新たな知的好奇心が芽生えるような、豊かな体験へと導くもの」です。決まった型に縛られず、実験的な試みが可能なコンテンポラリーダンスでは、より多様でボーダレスなコミュニケーションを追求できます。
つまり、踊る人の身体はたんなる表現の道具ではなく、他者と、そして世界と交信し、変化を促す力を持つメディアそのものなのです。
音楽を聴いて身体が自然に揺れ動く、あの原始的な感覚の先に、まだ見たことのない世界が広がっているかもしれない。そう思うと、私たちの身体が持つ可能性は無限だと感じられます。
今回の旅、いかがでしたでしょうか。4つの記事を巡ることで、「音と身体」の関係が、私たちが思うよりもずっと深く、豊かで、双方向的なコミュニケーションであることが見えてきたように思います。
私たちの身体は、音を感じ取り、音に癒され、音を発し、音で世界と対話する、驚くほど精巧な「共鳴体」なのかもしれません。
明日から、あなたの世界にあふれる音が、いつもと少し違って聴こえてきたら、うれしく思います。
※「キュレーション記事」は、フクロウナビで紹介されている各記事の内容をもとに書かれています。紹介する記事のなかには、記事が執筆されてから時間が経っているものもありますのでご注意ください