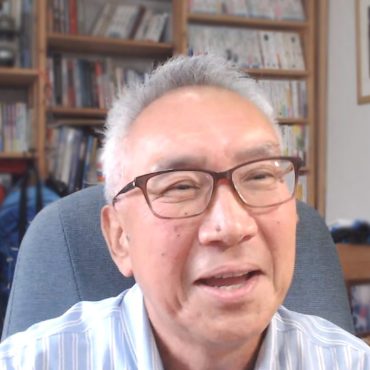生物・人間・私の「自己」ってなんだろう?自己観を刺激してくれる記事
増井 真那/慶應義塾大学先端生命科学研究所(修士課程)
「私」ってなんだろう?こんな疑問を持ったことはありませんか?
この遠大で茫漠とした問いは、どう取り組んだらいいかイメージしにくいものです。それはこの問いを考えていくと、「そもそも自己とは何か?」というさらに大きな問いに行き当たるからではないでしょうか。現代社会では、その昔に比べて生活や仕事、生き方における自由が大きく広がったことにより、「自分」を自由に形作ることができるようになりました。一方でこれは常に「自己」を見つめ直し、「自己をどう形作るか」を考え、試し続ける必要があるということでもあります。「自己実現」や「自分探し」などの言葉が踊るのは、今がそういう社会だからです。
今回は4つの記事を通して、生物/人間にとって「自己」とは何か?どう解釈できるか?どう捉えられるか?について考えてみようと思います。地球が誕生した46億年前、そこに生物は存在しません。ということは、「自己と非自己」を区別する主体がないので「自己」は存在しなかったことになります。「自己」というものは、生物がいて初めて存在するものと言えるでしょう。
それでは、生物の最も根本的なシステムとしての「自己」から見てみましょう。
記事をおすすめした人

増井 真那
慶應義塾大学先端生命科学研究所(修士課程)。5歳で変形菌に興味をもち、6歳から野生の変形菌の飼育を、7歳から研究を始め、小3で「変形菌の自他認識」という研究テーマを見出し今日まで取り組む。日本学生科学賞内閣総理大臣賞など受賞多数。著書に『変形菌ミクソヴァース』(集英社)など。
自己とは「膜」である!分離であり、交流である!
全ての生物は「膜」で外界と分離されることにより存在しています。もちろん人間も。言い換えれば生物とは、膜によって外界と区別されたシステムのことです。この膜による分離は「自己」の最も基礎的な部分と言えます。
そこでご紹介したいのが、筑波大学の菱田真史先生が取り組む「膜」の研究に関する記事です。膜というと1枚のシートを想像しますが、生物の持つ膜は内側と外側で2枚の二重構造になっていて、それぞれが内側のシステムを正しく保つ、外界との物質のやり取りを適切にするという異なる役割を担っています。
これが意味するのは、生物における膜の役割は「内と外の完全なる断絶」ではなく、むしろ「外界との交流を適切に行うこと」にあると言えるでしょう。膜で区切って内と外ができたそのときにはもう、自己にとって「外」とは交わるべきものだったことに気付かされます。生物における自己というものは、原初から今に至るまで、外部との交流を前提としていたのですね!
自己とは、変化し続けるものである!
私たちは「自己」を守りながら生きています。例えばインフルエンザウイルスのように有害な他者に侵入されると、私たちの体内では免疫系の働きが、それを攻撃し取り除いてくれます。つまり免疫系の根本は「自己と他者を見分ける」ことにあると言えるでしょう。
2つ目に紹介するのは、明治大学の鈴井正敏先生が取り組む免疫系の研究に関する記事です。興味深いことに、免疫系が捉える自己というのは常に一定のものではないというのです。免疫系は体内に侵入してきた他者を学習できるだけでなく、肉体を動かす自らの行動自体が免疫系の働きに変化をもたらすこともある。常に自己を守っている免疫系は、自己を規定するものであり、同時に自己を日々変えていくものでもある。 守ることは自己の固定ではなく変化。だから「自己」とは変化し続けるもの!ひとときもとどまらず、状況に応じたしなやかな「自己」を持っているのが生物の強さなのかもしれません。
自己とは、集団の揺らぎである!
ここまで見てきたように、どうやら自己というものは思ったよりも、周囲との関係性によって変化し続けるもののようです。それでは集団としてはどうでしょうか?
次にご紹介するのは、千葉大学の高橋佑磨先生が着目する「生物の少数派(マイノリティ)」に関する記事です。昆虫の集団の中に多様性があり、それによって集団そのものが安定性を得ているという研究が紹介されています。餌の探し方について複数のタイプが混在している集団は、単一の行動タイプだけで構成された集団よりも生産性や安定性が高いのだそうです。
これはちょっと意外に思えるかもしれません。多様性がある、マイノリティが存在するということは、つまりある生物の種の中に「揺らぎ」が存在するということ。どれ(誰)が優れているかという見方を超えて、揺らぎそのものが集団、そして種として重要なのだと気付かされます。この個体/集団における揺らぎは、長い目で見れば、種としての進化そのものとも言えるでしょう。そして揺らぎの源泉こそ、各々の持つ「自己」であることに思い当たるのです。
自己とは「自己と自己でないもの」の掛け合わせである!
ここで私たち人間の「自己」について考えてみようと思います。人間はもちろん生物の一種ですから、ここまでに挙げた自己の性質を備えています。しかしそれだけではなく、人間特有の自己のあり方も存在するでしょう。
最後に紹介するのは、明治大学の渡邊恵太先生による「自分が自分であるという感覚」の研究についての記事です。私たちは自分の体が「自己である」と認識できます。でも、この「自己である感」は、肉体を超えていくのだと言います。「使い心地の良い道具は、道具ではなくなる」のです。テニス選手が使いこなすラケットや、パソコンの画面上で動くカーソルですら自己という感覚の対象になるというのです。少々突飛に聞こえるかもしれませんが、実はこの感覚は誰でも身に覚えがあるのではないでしょうか。眼鏡や、今手にしているスマートフォンなどは「自分の一部」と感じるのでは?
人間は自らの認識により、肉体を超えて自己というものを拡張している!という視点で考えてみると、「拡張された自己」の広さを感じます。例えば、あなたの「推し」や故郷、母校なんてどうでしょう。私たちの「自己」は、とてつもなく大きく世界に広がっているのかもしれません。
私は研究者として、変形菌(粘菌)という生物の「自己」像の解明を通じて、生物にとって自己とは何かという問いの答えに迫ろうとしています。変形菌というシンプルなアメーバが自他を見分ける行動はとても不思議で、そこから「変形菌が持つ自己と他者を見分けるシステムは、免疫系のような他者の排除ではなく、融合してひとつの自分になれる『自己』を探すためにある」ということが見えてきました。
人間は、自分の「自己」への認識を新たにすることで自己のあり方を自在に変えることができると、私は考えています。今回の記事たちはどれも日々頭の中で悩むだけでは得られない、「自己」に対する幅広い視点を与えてくれました。私自身、変形菌の自己について新たな発見をするたびに、自分の「自己」観が更新・拡張されていくことを感じています。多面的な「自己」知に触れ、自己というものは常に一貫している必要はなく、もっと広く自由に捉えていいと考えることで、「自分ってなんだろう?どう生きていこう?」という(ときに重く苦しい)問いは、楽しいものになる。さらに、実際にそのような生活/生き方をすることができるかもしれない。そう思っています。
※「キュレーション記事」は、フクロウナビで紹介されている各記事の内容をもとに書かれています。紹介する記事のなかには、記事が執筆されてから時間が経っているものもありますのでご注意ください