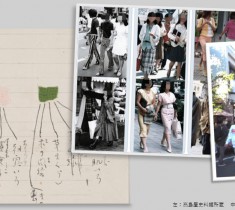現代なのに異世界!? 昭和カルチャーの魅力にふれる記事
タカ・タカアキ/「赤犬」ボーカル
「昭和がブーム!」と言われ、歌謡曲や当時の面影を残す飲食店が注目されるようになってから早や数年。昭和レトロを掘り起こす動きは途絶えることなく続いており、なんなら「そこに目をつけるのか!」と若い世代の着眼点に驚かされることも少なくない。同じ「現代」でありながら、もはやフィクションや異世界のように感じてしまうあの時代。当時を知らない世代をも魅了する昭和カルチャーのリバイバルとはなんなのか。4本の記事を紹介しながら考える。
記事をおすすめした人

タカ・タカアキ
大阪生まれ。1993年大阪芸術大学を中心に結成されたバンド・赤犬の二代目ボーカル。2015年公開の映画『味園ユニバース』には本人役で出演。大阪を中心に、各地のイベントやフェスなどのステージで活躍中。赤犬のコーラス部隊ナイトサパーズと共にイベントのMCなどもこなす。演歌雑誌の編集経験を持ち、昭和歌謡や演歌にも明るい。
リバイバルブームがもたらしたカルチャーの蘇生と進化
昭和が若者たちに面白がられるような、いわゆる「リバイバルブーム」は一定の周期で訪れ、一つのカルチャーが廃れた後、再び脚光を浴びて新たな層に普及するというサイクルを繰り返している。このリバイバルブームは、古いものを懐かしむ『懐古(=ノスタルジー)』と、そこに新たな解釈を加えて価値を再発見する『回顧(=レトロスペクティブ)』が組み合わさることによって生み出されると、関西学院大学の難波功士先生は唱える。
日本のリバイバルブームは、1980年前後に起きたフィフティーズやオールディーズのブームから始まり、少し後にモッズブームが訪れたことから、海外への憧れ+回顧がベースにあることが伺える。2000年代以降は映画『ALWAYS 三丁目の夕日』に代表されるような高度経済成長期へのノスタルジーが大きな割合を占めるように。近年ではシティポップやアニメなど日本発のコンテンツがSNSや動画コンテンツによって海外人気に火が点いて逆輸入されるという現象も起きている。
過去にばかり目をやっているのでは? と悲観的に捉えられることもあるリバイバルブームだが、サンプリングや再編集という概念が当たり前になった現代だからこそ、リバイバルブームは新たなカルチャーを生み出す原動力になり得ていると感じられる。
多様な業界を巻き込んだPR戦略。流行色が社会を塗り尽くした時代
流行色がカルチャーに与える影響は非常に大きい。共立女子短期大学の渡辺明日香先生は、ストリートファッションの定点観測に基づいて時代の移り変わりを研究しており、江戸時代からすでに庶民の間で流行色の概念があったことを説いている。明治期に入ってからは生活様式の西洋化を進める中、小学校で一時的に色彩の専門的な科目があったというのだから驚きを禁じ得ない。
大正〜昭和初期にかけては化学染料が普及したことで色彩革命が起こる。与謝野晶子や堀口大學ら文化人が百貨店の依頼で流行色を命名し、色に関する歌を詠んで、それが自社のPR誌に掲載されることで流行を生み出した。
第二次世界大戦が終結すると、1953年には日本流行色協会が発足し、業界をまたいだ流行色のPRが展開される。1960年代には、メディアで大々的に流行色が発表されると、業界をまたいだキャンペーンが行われ、世の中が一斉にその色で染まる状況があったという。
今回、紹介している記事の中で、1962年の流行色が「シャーベットトーン」だったことを初めて知った。もし過去に行ける能力があるなら、化粧品も家電も菓子もシャーベットトーンで統一されていたという世間の盛り上がりを体感してみたかったと思う。
心と体を癒す銭湯空間。チャレンジングな姿勢が次世代へのバトンを繋ぐ
昭和のカルチャーを語るうえで外せないものの一つに銭湯がある。現在では経営者の高齢化や設備の老朽化で大幅に数を減らしているが、フォークユニット・かぐや姫の名曲『神田川』でも歌われているように、かつて銭湯は日常生活の中でごく自然に存在するものだったのだ。
銭湯の灯を絶やすまいと奮闘している人も多い。東洋大学の記事に登場する東京・上野の銭湯「寿湯」の経営者・長沼亮三さんは東洋大学出身、元プロボクサーという異色の経歴の持ち主。祖父の代から銭湯を経営し、2人の兄も都内でそれぞれ銭湯経営を行っているという、まさに銭湯エリートな家系の出身なのだ。
近年、再注目されている銭湯だが、内風呂が普及した現代では、わざわざ足を運びたくなるような付加価値が必要となってくる。長沼さんは、セレクトショップ「BEAMS」とのコラボレーションでオリジナルの壁画を制作、「蕎麦つゆ風呂」などユニークなイベントを定期的に開催することで、常連も一見にも楽しんでもらいたいと語る。若き経営者の創意と工夫は銭湯のあり方をアップデートさせ、後世にもきっとその魅力を伝えてくれることだろう。私事で恐縮だが、週に3〜4日は銭湯で疲れを癒やしている者として、寿湯にはいつか訪れたいところだ。
店主のパッションを表現する純喫茶というキャンバス
昭和カルチャーの中で、銭湯、町中華に次いで再注目されているのが純喫茶。近畿大学のオウンドメディア「Kindai Picks」では、建築学科の高岡伸一先生によって昨今の純喫茶ブームの背景が解説されている。
明治末期に始まった日本の喫茶店は、昭和期に入って「純喫茶」というカテゴリーが生まれ、高度経済成長期にその数が急増。この時代に千日前の「純喫茶アメリカン」や梅田の「マヅラ」など、現在まで歴史を紡ぐ店舗が次々とオープンする。
これらの純喫茶は個性的な意匠が特徴だが、その要因は店主の思いを力技で反映した昭和の建築プロセスにある。純喫茶では時代に合わせて改修を重ね、採算度外視な高級資材が唐突に使われるなど、専門家から見ると脈略のないデザインになっていることも多い。しかし、それを上回る熱意でアップデートを繰り返してきたからこそ、純喫茶は、それぞれの店が唯一無二の空間を生み出してきたのだ。これは、システム化や便利さと引き換えに我々が失った最たるものだろう。
無駄を削ぎ落とし、引き算やミニマルな姿勢が評価される現代。デコラティブで「足し算こそ正義」という昭和の美学は純喫茶の中で生き続けている。
昭和の時代は高度経済成長やバブルなど、とにもかくにも「今を謳歌しよう!」という姿勢が強い。当事者たちは、まさか数十年後に自分たちの触れてきたものが再評価されるとは夢にも思わなかっただろう。
昭和のカルチャーは玉石混交ではあるが、そんな時代の中で生み出されたからこそ、長い時を経て掘り下げても、掘り下げきれないほどのエネルギーや新たな解釈に堪えられるだけの魅力を内包しているのかと思われる。次の世代は昭和のカルチャーをどのようにリミックスし、新たな形に変えるのか。今から楽しみでならない。
※「キュレーション記事」は、フクロウナビで紹介されている各記事の内容をもとに書かれています。紹介する記事のなかには、記事が執筆されてから時間が経っているものもありますのでご注意ください