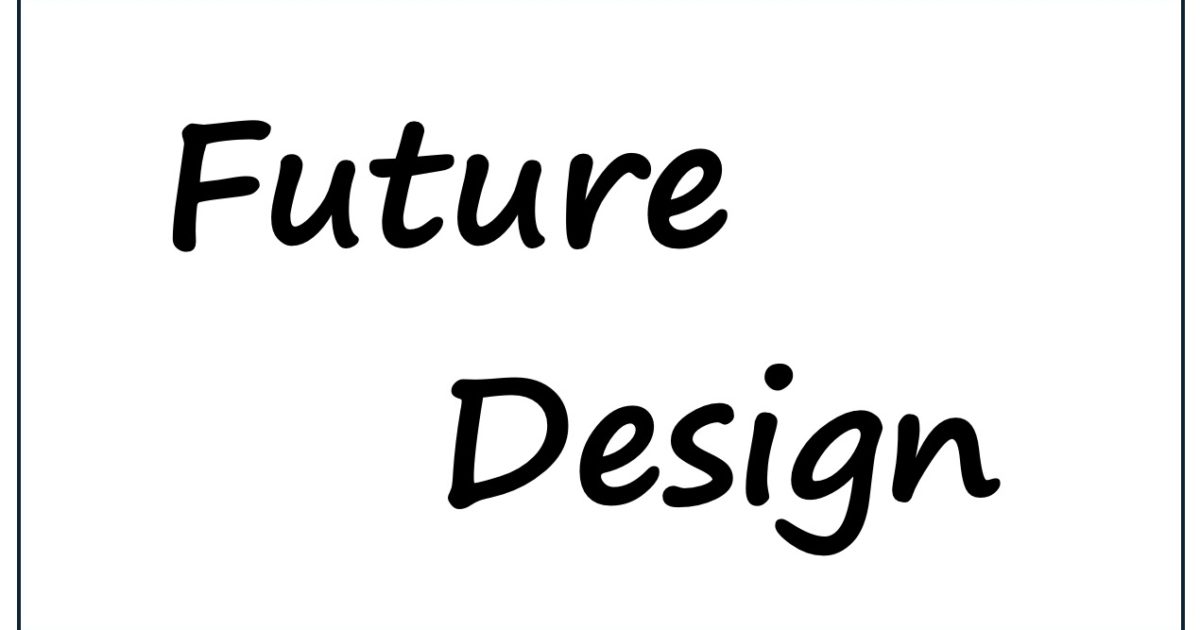みんなの知識を力に!参加するサイエンスコミュニケーションに出会う記事
山科 直子/筑波大学広報局 教授・サイエンスコミュニケーター
近年注目されている「サイエンスコミュニケーション」という言葉。難しい科学のことをわかりやすく説明すること、というイメージを持つ人も多いかもしれませんが、それだと、人々を、科学の専門家とそうでない人に分けてしまい、双方が交わることはなかなかありません。でも、だれでも大なり小なり科学に関わり、それなりの知識も持っているはず。多くの知恵や経験を持ち寄って科学を進めたり、方向性を考えるというのも大事なサイエンスコミュニケーションの一つです。みんなが参加することが力になる、そんなサイエンスコミュニケーションに出会う記事を3つ紹介します。
記事をおすすめした人

山科 直子
筑波大学広報局 教授/サイエンスコミュニケーター。化学メーカーで研究員を務めた後、日本科学未来館、東京大学大学院総合文化研究科 科学技術インタープリター養成プログラム等を経て、2013年より現職。研究成果プレスリリースの編集、研究者の紹介記事やポッドキャスト番組の制作、小中学生向けイベントの企画・実施などを通じたサイエンスコミュニケーション活動と、サイエンスコミュニケーターの育成に取り組む。
あなたが参加すると研究が進む
研究の世界にもクラウドソーシングのようなやり方があります。研究者に限らず、みんなで手分けをして、データを集めたり解析したりするものです。その一つが、京都大学古地震研究会などが実施している「みんなで翻刻」プロジェクトです。
何百年も前に書かれた古文書には、地震などの自然災害や、日食などの天文現象について記述されているものがあります。これらの中には、現在の地震や防災、天文研究にとって有用な情報が含まれていたりするので、いわゆる古典文学の読み解きとは違う意義があります。昔のくずし字や言い回しなどを理解するのは難しそうですが、AIの支援や他の参加者との連携もあるので大丈夫。研究者だけでは対応しきれない分量の歴史資料の読み解きが、みんなの力で可能になっています。異分野の研究をつなげるという点でも、サイエンスコミュニケーション的に興味深いですね。
市民の力を取り入れることで、研究に思いがけない進展が生まれたり、双方(市民同士も含めて)の相互理解がもたらされます。これこそサイエンスコミュニケーション。他にも、地域の生き物の季節変動をみんなでモニタリングするプロジェクトなどもありますよ。
あなたが参加すると研究が良くなる
「良い研究」とは何でしょう。研究そのものは真理の探究ですから、それ自体に優劣はありませんが、どんな研究も、その成果の使い方によって、良い研究にも悪い研究にもなり得ます。そう考えると、良い研究について、もっと考える必要がありそうです。そんな場を提供するのも、サイエンスコミュニケーションの役割です。
千葉大学大学院国際学術研究院の東島 仁先生が取り組んでいるのは、PPI(Patient and Public Involvement、研究への患者・市民参加)についての研究です。自分や家族が病気になったとき、いろいろ調べたり、治療方法を選択するのは、そうするべきだとわかっていても容易ではありません。ついつい、医師にお任せしたくなってしまうものです。しかし近年、患者や市民の意見を取り入れて研究する方が、患者にとっての良い研究が推進されるという考え方が登場してきました。
確かにその通り。でも、患者や病気の性質によっても異なる考え方があるでしょう。患者と医師だけでなく、医療の仕組みを支えるさまざまな市民も交えて、じっくり議論できる場を実現するPPIの仕組みの構築が望まれます。ちょっと荷は重いかもしれませんが、より良い研究、より良い医療につながるのなら、参加する価値はありますよね。
あなたが参加すると科学が良くなる
インターネットや携帯電話がそうだったように、新しい科学技術の登場が、社会の様相を一変させることは少なくありません。どんなふうに過去の社会が変わったのか、そして未来の社会が変わりうるのか、サイエンスコミュニケーションは、そういった議論も扱います。
立命館大学食マネジメント学部の西村直子先生が試みている「フューチャー・デザイン」という手法では、未来人になりきって社会課題を考えます。まちのインフラをどのように整備していくか、といった問題は、住民同士でいくら議論をしてもまとまりにくいものですが、未来人の立場で考えると、現在の課題が明確になり、解決策が見えてくるのだそうです。
このフューチャー・デザインは、もともと経済学の分野で提唱された手法ですが、新しい科学技術を社会実装する際の課題解決にも有効だと思うのです。自動運転車やAIなどが実用化される時には、さまざまな利害関係や対立が生じます。エネルギーや廃棄物の問題も、多様な意見があって、なかなか解決の道が見えてきません。みんなが参加して、少し俯瞰した視点で将来を見据えた議論ができれば、より良い科学のあり方への道筋が見えてくるのでは、とちょっと期待しています。
サイエンスコミュニケーションは、科学に親しむだけではなく、究極的には社会を動かす力を持っている…と、私は信じています。科学の専門知識はなくても、だれでも何かしらの得意分野があるはず。一見無関係そうな知識や日常の知恵が、意外と科学の役にたったりするものです。みんなが参加することには、そういう意義があるんです。
とはいえ、今回ご紹介した記事はどれも、サイエンスコミュニケーションを意識したものではないと思います。いろんな形で、いつのまにかサイエンスコミュニケーションがあちこちで行われているというのが、理想形なのかもしれませんね。
※「キュレーション記事」は、フクロウナビで紹介されている各記事の内容をもとに書かれています。紹介する記事のなかには、記事が執筆されてから時間が経っているものもありますのでご注意ください